第1回 公益法人会計基準の本質
1.複式簿記の本質
(5)資本等式と貸借対照表等式
資本等式と貸借対照表等式
企業会計についての簿記の入門書は、資産、負債、資本について、財産と債務とそれらの差額という説明をとりあえずのものとして行い、いきなり現金に関する仕訳に入っていきます。
習うより慣れろ、まず、簡単な仕訳をともかく覚えなさいというやり方です。しかし、勘定科目を借方に書くか貸方に書くかの判断はそれだけの理屈では明らかではなく、結局、簿記の八要素を丸暗記し、取引毎に当てはめていくしかありません。これは非常に苦痛な事です。現預金など、わかりやすい科目がどちらにくるかを決めてから、相手勘定を考えるといったテクニックが重要になってしまうのです。
企業会計において勘定科目を借方貸方のどちらに書くかを決定するための基本的な理屈は、資本等式あるいは貸借対照表等式にあります。
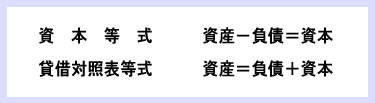
資本等式とは
資本等式と貸借対照表等式は、単に負債を左辺から右辺に移項したもののように見えますが、全く違った概念に基づいています。資本等式は、財産=資本という等式を基本とし、資本を増加させるものを積極財産(資産)とし、資本を減少させるものを消極財産(負債)として、その差額が正味財産(資本)であるとする考え方です。
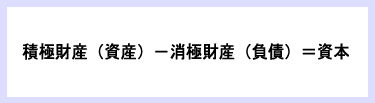
企業は出資者のものであり、その立場から、資本を考えると、所有する財産から債務を引いたものが出資者のもの、つまり、資本となるのです。これは企業主主体論と呼ばれる考え方からきています。
原始的には、出資者を募り、商品を仕入れ、船を借りて他の港へ航海を行い、そこで商品を売りさばいて得た現金で、現地の商品を仕入れる。さらに航海を行って元の港に戻り、商品を売りさばく。最終的に残った現金と最初の現金との差額が、利益というわけです。その過程で作られる諸表も、最終処分を前提としてその価値が判断されることになります。企業を常に出資者のものとして考える訳です。
貸借対照表等式とは
貸借対照表等式も、財産=資本という考え方からスタートする事は同じです。しかし、財産を、企業が運用する全ての価値と捉え、その調達方法の分類として、他人資本と自己資本に分けるのです。資本主または株主から調達したもの、および企業がその活動の結果として蓄積したものが、自己資本であり、債権者から調達したものが、他人資本という訳です。

財産を企業が運用するすべての価値として捉えるという事について、簿記新論では次のように述べています。少し長いですが、引用します。
「この関係を、価値の現象形態の側から、ながめるならば、次の如く、いえる。有形財貨や権利等から、その具体的な形態を捨象するならば、それらのものは、一様に、価値として捉えられる。」
商品にしても、売掛債権、手形債権、土地、建物にしても、
「それらの有形財貨や権利の内容にどのような変化が生じようとも、価値の面から見れば、それは単なる外面的変化に過ぎないのであって、そこに、常に流動的な財産に対して、常に変わらない「価値の存在」という事実を、指摘することができるのである。企業について、とらえられる、そのような価値の全体が「資本」と呼ばれていることは、周知のごとくである。
調達の側から見れば、
「負債が、企業にとっての負担を意味する将来の支払い義務として見る以上に、そのような性質を、単に資本調達に付随して生じる条件に過ぎないと考え、そのような条件で調達された資金が、資本として機能する側面を重視するのである。」
企業の経営状態をあらわす指標として、総資本利益率というものが使われます。この場合の総資本とは資産総額をさしています。このことからも、現在の会計学で価値(資産)=資本という捉え方が一般的だということがわかります。
企業が運用する価値の全体を、一体のものとして把握し、調達方法の違いとして、自己資本と他人資本に分類するという、この考え方は、企業主体論と呼ばれる考え方を基本にしています。企業を出資者や株主の所有物として考えるのではなく、社会的存在となった企業そのものの視点から捉えようというものです。
財産を最終処分の観点からではなく、 日々流動する価値の総体として考えるのです。企業は一航海で終了するようなものではなく、継続企業体として活動を行い、永続的に価値を増加させていく存在として認識されます。従って、一定期間(決算年度)を定め、その期間に企業の所有する価値がどう変化したか、他人資本はどう変化したか、その結果自己資本はどう変化したかについての報告のため、推定計算を含む期間計算を行って、財務諸表を作成するのです。
財務諸表の役割
財務諸表の作成目的も、出資者や株主のためだけではなく、企業を取り巻く多数の利害関係者を意識したものとなります。企業の営業努力で得られた処分可能額の計算は、株主に対する配当可能額だけはでなく、経営者への配分である役員賞与の額、企業の継続と成長のための積立額を含んだものとなります。
債権者にとっては、債権の保全のため、必要な資産が保持されているか、今後の取引規模を考えるため、その企業がどの程度の超過収益力をもち、どの程度の成長力を持っているのかを判断するための資料になります。資本と経営の分離がより進んでいる、株式が公開されている企業については、より多くの投資家が、企業を支配する目的ではなくより多くの配当を得るために、あるいは株式の値上がりを見込んで、その企業の株式を売買します。
その場合の判断材料として、財務諸表は重要な役割を果たします。国家にとっても、その企業に対する課税額を決定する根拠となるのは財務諸表です。入札資格を判定する場合も財務諸表が利用されます。
最近では、その企業が環境問題に対してどのように配慮した経営を行っているかを、商品購入の参考にする動きがヨーロッパを中心としてみられます。その場合の判断材料になるのも、財務諸表を含む決算報告書です。企業が利益を追求するだけでなく、社会的責任をどう果たしているかを監視する。このような動きは、今後、ますます増加していくことでしょう。
もっとも、実質的な個人企業であるような株式会社や有限会社では、いまだに企業主主体論の方が、あてはまる場合もあります。オーナーであり、社長である人の権限は絶対です。しかし、長期的にみれば、そのような企業は淘汰されていきます。日本の会社の平均寿命が50年というのは、そのような社長の活動寿命に、等しいのではないでしょうか。
いずれにせよ、近代会計学では、貸借対照表等式から考えるのが、より正しいと言われています。
